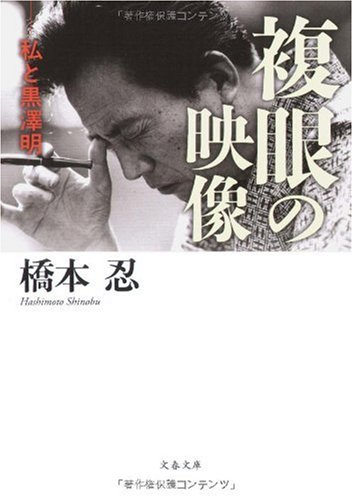ここでは題名と名称を恣意的に表記します。[敬称略]

ストーリー
風俗嬢の道子は、琵琶湖の湖畔を愛犬のシロを追って走り続け、1年以上が過ぎた。かつて、仕事に疲れ、失意のどん底にいた道子はみすぼらしい野良犬のシロとの出会いに運命的なものを感じた。そして、銀行員の倉田からジョギングシューズを贈られたことがもう一つの刺激となって、本格的なジョギングを始めたのだった。8月末のある日、葛篭尾崎の先端で道子は狂おしい笛の音に誘われ笛を吹く男・長尾に出会った。私はこの人に会うためにシロに導かれ走っていたのでは……。
スタッフ
原作・脚本・監督 橋本忍
製作 佐藤正之 大山勝美 野村芳太郎 橋本忍
撮影 中尾駿一郎 斎藤孝雄 岸本正広
美術 村木与四郎 竹中和雄
音楽 芥川也寸志
録音 吉田庄太郎
編集 小川信夫1982年製作/164分/日本
映画.comより引用
今回はネタバレなしの懐かしオチャラケ解説モード。
エブエブ、アカデミー賞7部門受賞おめでとうございます。
さて前回、彼の国での超変な映画の感想を書いたので、日本の変な映画もやらなければフェアじゃないだろうと考えて、「変な映画ならこれだろ」と超ひさしぶりに2回目の鑑賞となったが……
アレ?思ってよりもまともなじゃないか。
……………
ヤバい、変を感知する部分が麻痺している。
恐るべきエブエブ!
いやマテ、「愛犬殺され復讐」は『ジョン・ウィック』(2014)で復活したし、意外とこれは時代が追いついてきたとかか?
…………無いな。
と、独り三文芝居はそこまでして、コノ作品は映画ファンにとってはいわゆるヘッポコ大作という評価になっていて、その原因は脚本・監督の橋本忍の勝手が過ぎたというところで落ち着いてはいて、確かに物語は意味不明なのだが、「愛犬を殺されての復讐劇」ドラマとしてはそんなに変ではなかったし、ヘッポコでもなかった。
感情の流れとしてはすんなりと落ち着く。
ちまたでは、物語=ドラマなのだろうが、物語はあくまでもはじまった!終わったという観客にケジメをつけるものであれば、ドラマとはソレを観ている者、つまり観客の心理・心を揺り動かしてある方向へと導くからだ。だから、このブログで自分は物語とドラマを切り離して書くことが多い。
もうチョイと説明すると、ドラマとはその人らしさを宿している精神的背景と持つ人物が、理不尽な目にあったときにどう行動するのかを示すモノだからだ。そしてその作品内における個々の登場人物達の感情のフローチャートをそれれぞれに絡めることによって情念が生まれて流れて、感動に導かれる。それがドラマ。
だから、それを感じ取れれば舞台が時代劇でもSFでも、見た目は時代劇でもシュールなドラマだったりしても、情念が流れ、その落とし所が巧くゆき観客に伝えることができれば、エブエブみたいに物語に属する設定を多くしても感動するようになっている。
ぶっちゃけ、親と娘のドラマがちゃんと伝われば、ブラックホールに落ちて本棚に後ろ側に着いちゃう『インターステラー』(2014)でも大丈夫だって話だ。
ジャンル映画の評価で一般人がよくする、これはただの〇〇(←お好きなジャンルを入れろ)ではない。というのはそうゆう事だ。
なら、どうしてコイツがヘッポコの評価を受けたのか?
その答えはドラマが斬新すぎた。
もう少し付け加えると、情念の流れるドラマは巧くいっても、観客を納得させる物語は破綻している。という事実になる。
実は、答えは自分のモノではなくて、脚本・監督の橋本忍自身が気かついていて、迷ってそれを『砂の器』の野村芳太郎監督に読ませたら……
ドラマの質がこれまでにない、全く新しいもので、従来の映画の感覚や理論では判断の余地がなく、正直に言って自分にもよく分からない。このホンの善し悪しは出来上がった映画を見ないと、誰にも分からないのでなかろうか。
こんな感じ。その後に、ドラマを通すばかりに物語に無理がとおりすぎておかしくなっている。と橋本自身が告白している。
ちなみに、著書ではその後に当時の黒澤明の代表作であった『影武者』や『乱』のチョイ批判に入るのだが、それはさておき、このあたりの話から見えてくるのは、橋本忍といえば、日本どころか世界でも指折りの脚本家だが、やはり名脚本家であって名監督ではない。という事実だ。
斬新なドラマを書けても、それを具体的にどう撮るかのイメージがなされていないからだ。これが一緒に仕事をしたことがある黒澤明とか『切腹』の小林正樹なら撮るイメージができていたなら、それをやるだろうし、イメージができていなければ、書き直しを要求するか断るに決まっている。野村にはそのイメージがわかなかった訳だ。だから、そんな言い方になった。
なのに、そのイメージができていないのにズルズルと流れるままに橋本は撮ってしまった。これが、コノ作品がヘッポコの烙印を押された大きな理由なのは間違いはない。
ドラマ作家としての直感は持ち合わせていても、映像作家としての直感は持ち合わせていなかった現実が『幻の湖』には反映されている。

結論:イメージがわかないものは絶対に撮るな。逆にどんなに物語がおかしくてもイメージがあるなら、それは撮れ。評価はどうであれ、それはドラマとしてはうまくゆく。
そんな終わりです。
‐‐ 余談だけども、物語とドラマが乖離しすぎていていても、それを繋ぐ知識さえあれば何とかなるってケースはある。コノ作品だとSFやファンタジーの知識が橋本にあったのなら何とかまとまった作品になったのかも。
DVDで鑑賞。
![幻の湖 [Blu-ray] 幻の湖 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ttLHd1YiL._SL500_.jpg)