ここでは題名と名称を恣意的に表記します。[敬称略]
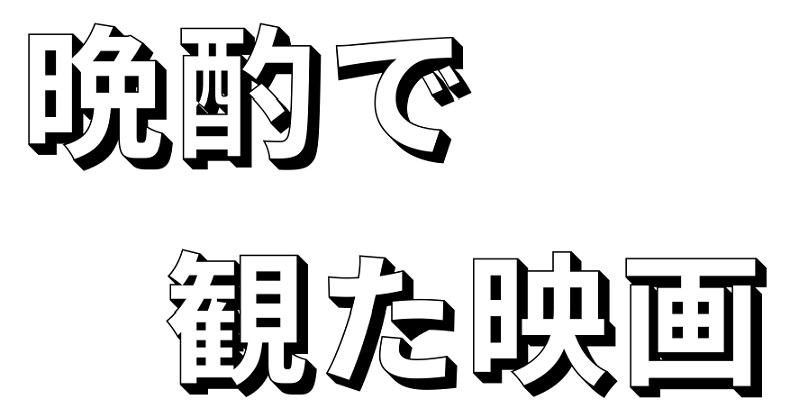
さて、前回『猿の惑星 キングダム』について書いたから、やはりこれもやっとこうかなって。

いきなりネタバレからはじまる。
今さらだが、コノ物語は宇宙を探検していた主人公タイラー等がある惑星へ緊急着陸してその地をさまよっていたら、そこは知能が発達して言葉を喋る猿が支配者で知能のない人間は彼らからは動物扱いだったというショッキングな設定ではじまり、言葉を喋る猿とタイラーが出会い、この星に潜む秘密に近づいてゆく流れになっている。
まぁ、今や映画ファンなら内容は知らなくても、これがコノ作品『猿の惑星』(1968)だというのは知っているくらいに象徴的なカットになった。
とはいえ、この映像インパクトのせいでコノ作品の本質・ドラマが分かりにくくなっているのは確かで、今回はそれを二つに分けて語ってみたい。
でも、その前に前提として、原作者とコノ作品の脚本を書いた二人の脚本家について掻い摘んで語らねばならない。
原作はピエール・プール。

プールはフランス人作家で代表作は『猿の惑星』と『戦場にかける橋』。第二次世界大戦では自由フランス軍として戦い日本軍の捕虜となった過去がある。つまり原作の猿とは日本人の隠喩であることは誰にでもすぐに思い浮かぶことができる。
しかし、原作のラストも捻りが効いているとはいえ、衝撃的とまではいかない。
その原作を映画に直したのはアメリカの脚本家ロッド・サーリング。

サーリングといえばテレビシリーズ『ミステリーゾーン(トワイライトゾーン)』のホストで名を知られているが、そこで取り上げた題材は社会問題をSF風ファンタジー風にしたものが多く作風としてはリベラルと言っても良い。
そのサーリングも太平洋戦争では日本軍と戦っている過去があるが、コノ作品では当時のアメリカ世相を取り入れて強烈なインパクトに仕立て直した。
— 余談だが、トワイライトゾーンのあるエピソードでコノ作品のラストらしきアイディアは表れているので、それをドレスアップしたと見るべきだろう。ちなみにネタバレになるのでどのエピソードとかは言わない。
だが、サーリングの脚本(脚色)は猿の世界が未来で描かれていて予算を大幅に使うものであったためシェイプアップをする必要に迫られて、その役割りを担ったのは同業者のマイケル・ウィルソンだった。

ウィルソンは1950年代にあった左翼運動を糾弾する赤狩りにおけるハリウッドブラックリストに載っていた人物であるので思想的には保守というよりもリベラルよりで、実は『戦場にかける橋』(1957)の脚色も手掛けているので(カール・フォアマンと共同)プールともすでに繋がっている。そんな彼が監督の意向でサーリングのインパクトは残しつつ舞台設定を未来から原始風に書き直した。
— またまた余談だが、コノ作品でチンパンジーのジーラ博士で出演しているキム・ハンターとオランウータンのザイラス博士で出演をしているエドワード・G・ロビンソンもウィルソンと同様にハリウッドブラックリストに名が入っている。
こうして、我々が知る『猿の惑星』はほぼ完成した。
さて、長々とした前振りは終って本題である二つの要素について入る。
◯ ブラックパワーへの恐れ
それまではアメリカの黒人と白人は法律上で不公平が存在した、しかし1964年アメリカ公民権法成立でそれも無くなった。しかし、社会は慣例・慣習で黒人を受け入れられない体勢だったのでそれを打破するために起こした運動がブラックパワーだ。キング牧師やマルコムXもここから歴史に名を残した。
コノ作品では、当時の台頭していたブラックパワーに対する白人保守層の恐怖の感覚を描いている。作中で猿達が人間を猟るシーンがあるが、これは露骨に白人達がアフリカで黒人を奴隷として猟っていたのと同じだ。

ココには、そんな白人支配層の苛立ちが表れている。
〇 人間と猿の起源への恐怖
コノ作品では、主人公のタイラーが猿と会話できる知能を持っているためにジーラとコーネリアスの二人の猿の科学者が弁護というよりも、持論である「猿と人間は同じ種から分離した」説を展開するのだが、これが何を意味しているのかといえば、ズバリ「進化論裁判」だ。
ダーウィンの進化論に対する宗教による反対論は進化論の誕生から存在したが、それが一般化したのは進化論を教える事を禁じていたアメリカテネシー川の生物高校教師のスコープスがそれに反して進化論を教えたことからはじまった1925年のスコープス裁判。そこから科学の立場の進化論者と聖書の教えに基づく反進化論者との争いは今でも続いているが、これがココでは描かれている。
あと、ちょっと付け加えるとしたら主人公テイラーをマッチョな男性としてキャラメイクしているのも白人男性の理想像の定型化になっている。また演じているのはチャールトン・ヘストンなので逞しい胸板もコノ作品の見どころのひとつになっている。

このふたつを考慮に入れて、あのラストカットを振り返れば別の感想に落ち着く。
白人支配層への批判。
白人支配層は愚かだ。
もっとぶっちゃけたら、白人支配層の考えはすべて間違っている。
まぁ、穏当にするなら、慣習に支配されている社会のマジョリティに対する批判になる。
これが、あのラストシーンの真意だ。
とはいえ、コノ作品は世界的に大ヒット作なので、ヒット作の宿命で続編が作られてやがてシリーズ化された。映画化をしたスタジオが別の大作で失敗続きだったので、その損失を挽回するかの如く素人でもわかるくらいに予算が少なくなってゆくのが見え、社会情勢も変化していったのでコノ作品にあったメッセージ性は徐々に変わっていったのである。
コメント欄にご指摘があった通りザイアス博士はエドワード・G・ロビンソンではなくモーリス・エヴァンスが演じていました。ここで謹んでお詫びと共に訂正いたします。
BDで鑑賞。
スタッフ
監督:フランクリン・J・シャフナー
脚本:マイケル・ウィルソン ロッド・サーリング
原作:ピエール・ブール
製作:アーサー・P・ジェイコブス
音楽:ジェリー・ゴールドスミス
撮影:レオン・シャムロイ
編集:ヒュー・S・ファウラー
Wikipediaより引用
![猿の惑星 ブルーレイBOX (FOX HERO COLLECTION) (6枚組)(初回生産限定) [Blu-ray] 猿の惑星 ブルーレイBOX (FOX HERO COLLECTION) (6枚組)(初回生産限定) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51PTYVNDkeL._SL500_.jpg)
![猿の惑星 [Blu-ray] 猿の惑星 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/510bCe32qsL._SL500_.jpg)